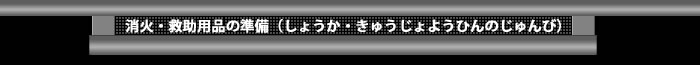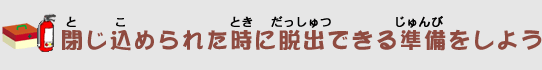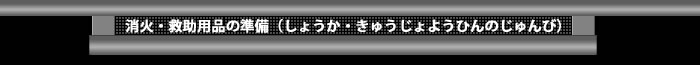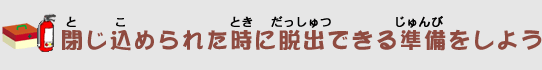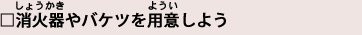
消火器(しょうかき)やバケツを用意(ようい)しましょう。また、お風呂(ふろ)には常(つね)に水(みず)をためておきましょう。ただし、お風呂(ふろ)にためておいた水でおぼれないように、お風呂場(ふろば)で遊(あそ)ぶのはやめましょう 。消火用水(しょうかようすい)や断水時(だんすいじ)の生活(せいかつ)用水[トイレなど]としても使(つか)えて便利(べんり)です。
火を消(け)すチャンスは3回(かい)あります。身(み)の安全(あんぜん)を確保(かくほ)してケガをしないように消火しましょう。
(1)一番目(いちばんめ)は、揺(ゆ)れ始(はじ)めです。
緊急地震速報(きんきゅうじしんそくほう)を見聞きしたときに、すぐに火を消すことができれば、コンロやストーブなどの火を消しましょう。 ただし、揺れ始めたときに熱湯(ねっとう)をかぶったり、倒れてきたストーブなどで火傷(やけど)をする危険(きけん)もあるので、決して 無理(むり)をせず、火元(ひもと)から離れることも大切です。
(2)次(つぎ)の機会(きかい)は、揺れがおさまった時(とき)です。
揺れの激(はげ)しいときに、無理(むり)をして消火する必要(ひつよう)はありません。揺れがおさまってから落(お)ち着(つ)いて火を消しましょう。
(3)最後(さいご)は、火災(かさい)が発生(はっせい)した直後(ちょくご)です。
火事が起(お)こったすぐ後(あと)は炎(ほのお)も大(おお)きくないので、消火器等(など)で十分(じゅうぶん)消火することが可能(かのう)です。 |